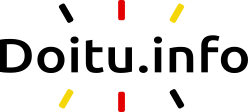ブログをはじめました
ブログ始めました
はじめまして。ドイツに関する生活ネタ情報やシステム開発関連の記事を投稿していきたいなと思い、このブログを作成しました。 ご多分に漏れず、今まで幾つかのブログサービスでブログを始めてはスグに更新を止めてしまうということを繰り返してきました。 今後はそのような事がないように頑張りたいと思います。
誰?
現在ドイツの現地企業でWebデベロッパー兼システム・アドミニストレータとして働いているアラサーおじさんです。 すでにドイツに来て6年、今の会社に就職してから5年が経過しました。 ドイツ語力は。。。現地に来れば誰でもその国の言葉が喋れるようになる!というのは嘘ですね。
何故ブログを始めるのか
幾つか目的が有ります。
日本語力の向上
日本人が一体何をって言っているのだ?と思われるかもしれませんが、どうも20歳ごろから比べると文章構成能力が落ちてきてしまっているように感じています。 三つ子の魂的に、当然母語である日本語を忘れることは無いとは思いますが、普段ある程度まとまったの量の日本語文章をアウトプットする環境に居ないので、どうしても社会人になってから身につけたような、しっかりした日本語文章を書く能力が落ちてきてしまっているようです。
TwitterなどのSNSは利用していますが、こちらなどはあまりしっかり考えずに文章を垂れ流しているのでそれも原因の一つかもしれません。 そのため、このような形でブログを書くようにすれば必然的にまとまった量の日本語文章のアウトプットが増えるので日本語能力の意地&向上が計れるかな、と思った次第です。
日々の生活を形として残したい
すでに6年ドイツで生活しているので、さすがに新鮮味は失われていますが、それでも「これは日本にはない面白いものだなぁ」というモノに出会います。 そういった目で見たり実際に感じたことを何か形として残していかないと勿体無いなと思い、これもこのブログを立ち上げる一つの動機になっています。
技術的な実験の場
詳細は後述しますが、このブログ自体は全て自分でフルスクラッチで作成したものです。 Bloggerやはてなブログなどの既存のブログサービスはもちろん、WordPressといったブログシステムも利用していません。 私の仕事であるWeb開発はかなり流れの速い業界なので、日々新しい技術やツール、方法論などが生まれています。 これらをキャッチアップしていくためには当然実際に使ってみるのが一番なのですが、やはり普段の仕事では中々それを試す機会というのは限られてきます。 そこで、このブログの構築運用を通してそういった新しい技術などをこのブログで試してきたいなと思っています。
そして面白ネタなどをある程度の数公開できた時点で、邪魔にならない範囲でGoogleアドセンス等を設定してどれぐらいの成果が得られるのか、ということにもチャレンジしていきたいと思っています。 ただ、実際に発生するインセンティブよりも、そのインセンティブを発生させるために必要なこのブログの閲覧者の方の利便性を如何に向上させていくか、そしてそのため必要なマーケティングに関する知識や技術力の向上こそが真の目的です。
情報発信のベース
あとは幾つか小さなWebサービスなんかをチョコチョコ公開していきたいな~と思っているので、そのための情報発信のベースとしてこのブログを位置づけようと思っています。
技術情報
すでに上で書きましたが、自分が普段使っていない新しい技術などを利用してしまえば技術力の向上が計れるぞ!ということで、このブログは全てフルスクラッチで自分で書き上げました。 利用している環境を大雑把に羅列すると以下のようになります。
- Linux / Ubuntu
- Docker
- Vue.js / Nuxt.js
- Express
- Node.js
- Nginx
- axios
- scss
- MongoDB
- Bulma CSS
- Git
- Inkscape(ロゴ、favicon、apple-touch-icon)
普段はサーバサイドのお仕事がメインなので、思い切ってモダンなフロントエンド開発環境を試してみました。 色々試行錯誤しながら作ったので大体1ヶ月ほどかかりました。
やはり自分で全て作ると細かい部分まで自分で作り込める(作りこまないとダメ。。。)のが嬉しいですね。 ブログ記事は全てMarkdownで記述できるようにしています。 そのためにmarkedとうMarkdownエディタのためのライブラリを利用しています。 さらに、この記事の右側に表示している目次部分はこのmarked経由で生成するように自分で実装しました。この目次機能はかなり気に入っています。(スマホやタブレットなど画面が小さい端末だと非表示にしています)
一番の気付き
Nuxt.jsとExpressというところからお分かりいただけるように、このブログはサーバサイドレンダリング(以下SSR)でフロントエンドを表示しつつ、バックエンドのRESTful API自体も同じNode.jsサーバ上で動かしています。
1点だけ重要なポイントを上げるとすれば、フロントエンド/SSRサーバとRESTful APIサーバは物理的に分けるべきだった、この一言に付きます。 今までNode.jsの経験が皆無だったので、技術検証の目的もあり、RESTful APIサーバもフロントエンド/SSRサーバを動かしている同じNode.js上で動くようにしました。 問題なく動いてはいますが、これはかなりハマりポイントが多かったです。 特にJWTベースの認証方式を採用しているので、クライアント(ブラウザ)からRESTful APIを叩くのは問題ないのですが、SSRのタイミグだとRESTful APIを叩くためのJWTトークンが当然SSRサーバには存在しない、という点に大いに苦しめられました。
この辺りは自分のNode.js等への理解力不足が主な要因ですので、そういった意味ではこれらの問題点の洗い出しと解決方法を検討することが出来たのでチャレンジしてみて本当に良かったと思っています。
Node.jsでC10K問題に対応できる!というのはこのブログには全く関係ないので、バックエンドのRESTful APIサーバは恐らくPythonで書き直す事になると思います。(そう!Pythonも絶賛勉強中です!)
今後の予定
基本的にはゆるーい感じのドイツ生活ネタ情報を投稿してきたいなと思います。 時々システム開発関連の事も投稿しようとは思っていますが、ちょっとこの辺りのバランス感は今後色々実際にブログを運用しつつ調整していきたいなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
公開日:2018/02/16